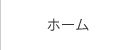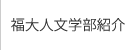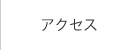2009年懸賞エッセイ:特選作品 「仕事と私」久保結さん
2010/05/23
「仕事と私」
LA071355 久保結
幼い頃、「仕事」と聞けば、まず思い浮かべていたのは父の背中だった。父はパソコン
量販店に勤めていて、その働きぶりは娘の私から見ても熱心そのものだったのだ。
むしろ熱心を超えて、「働き過ぎ」とさえ感じていたように思う。朝から晩まで働き詰め
なのに、下手をすると日曜日も一日家を出ていて、帰ってきたと思えば「店の周囲を
掃除してきた」などと言う父を見れば、そうなるのも仕方ないだろう。休日なのに何故、
やれと言われたのか、給料のためか、疑問をぶつける私に父は「そういうことじゃないよ」
としか答えてくれなかった。家よりむしろ会社に居ることの方が多く、滅多に遊んでくれ
ない父を見て、私の「仕事」に対するイメージは非常に悪かった。「仕事」と言うものは、
何か大きく強い怪物のようなやつで、父を無理矢理奪ってしまっているんだと思うと
腹立たしかったのである。
今こうして成長した私の「仕事」のイメージは、もちろんそんな荒唐無稽な幼児の想像
ではない。年を重ねるに従って「仕事」という言葉が現実味を持って迫ってくるように
なったからだ。三年次ともなれば、「就職」という言葉を見ず聞かずには生活はできない。
同級生も私も早く確実に自分の「仕事」を見つけなくてはと焦燥に駆られているので
ある。ここでの「仕事」は「生計を立てるための生業」というイメージになるだろうか。
不況への不安も強く、安定した生活のために必死で追い求めているのが私たちの
「仕事」だ。
「生計を立てる」つまり「金を稼ぐ」という意味合いになってくると、現時点の私の中で
「仕事」という言葉は「アルバイト」に結びついていく。自分の周囲のことくらいは自分で
世話をしなければと思い、深く考えずに始めたアルバイトだが、これによって私は「仕事」
が「金を稼ぐ」だけのものでないと気づかされることになった。
アルバイトを始めた当初は「仕事」をとても辛く感じていた。覚えるべきことの多さに混乱
し、先輩や上司に嗜められることも多く、何もできていない自分が情けなかった。幼い頃
父の向こうに見た怪物を再び見るようだった。しかし、職場に慣れて積極的な行動を取れ
るようになると、たちまち状況は変わった。アルバイトに向かうことが楽しみで仕方なく
なったのである。何故なら、「仕事」に慣れるにつれ、周囲から信頼を得ることに成功し、
自分なりの「やり方」を大きく認められるに至ったからだった。働くことにおいて、信頼され
るということは労働量や責任がどっと増えることである。もちろんそれが怖くないわけでは
ない。だが自分の「やり方」を確立できるというのは何事にも代えがたい喜びだと私は
思う。人の信頼が私に自信を与え、私の「やり方」を作ったのである。
この「やり方」は、「自分のスタイル」という言葉で言い換えたい。自信に基づいた「自分
のスタイル」を貫くために人は働くのではないか。アルバイトとして働きながら、私は
「仕事」に対してそう思っている。「仕事」に励めば励むほど「自分のスタイル」が確立され
ていく。逆に「仕事」を疎かにし、人に信頼されず、むしろ依存し、その結果成果も報酬も
ついてこなければ、「自分のスタイル」を貫くのは難しいだろう。私たちが「仕事」と聞いて
すぐ思い描く「職業・生業」というイメージは言わば「仕事」の内周であり、実は「自分のス
タイル」の確立という外周が存在するのではないかと思う。
これが今私が思う「仕事」である。今なら私にも、父の「そういうことじゃないよ」という答え
が理解できる気がする。「仕事」は怪物のような力で私に何かを強制するものではない。
これからのアルバイトも、就職した後も、これからのどんな「仕事」にも「自分のスタイル」
を作っていくために励みたい。